前回、資本蓄積過程において資本の規模の拡大とともに資本の質的構成がどのように変化するのかについて述べましたが、実はこのような資本の蓄積過程で労働者人口において大きな変化が生まれるのです。
結論的に言いますと、一定の失業人口が生まれるのです。
そこで、今回は資本の蓄積がどのようにして失業人口を生み出すのか、その仕組みについて考察してみます。
資本の有機的構成の高度化と相対的過剰人口
すでにみたように、資本の蓄積がおこなわれ生産に機械が導入されるにつれて、資本の有機的構成が高まります。言い換えれば、総資本のうち不変資本の割合が大きくなり、反対に可変資本の比率が小さくなります。
労働力に対する需要は、直接には可変資本の大きさによって決まりますので、資本の有機的構成が高まるにつれ、労働力に対する需要は相対的に減少していかざるを得ません。
このように、労働力に対する需要は資本蓄積が進むにつれ相対的に減少するのです。
ところが、その反面に資本主義が成長していくにつれ働き場を求める労働者は急速に増えていきます。というのは、企業間の競争によって吸収・合併や倒産する企業も増えて、雇用労働者の減少への圧力が高まるのです。また、経済成長により人口の自然増加も加わることによって、全体として労働供給主体が増えていくのです。
このようにして、資本の蓄積過程で一方では供給主体である労働者の絶対的な数は増えるのですが、他方では労働力に対する需要は減ることによって、需給ギャップが生じるのです。
この需給ギャップによって失業人口が発生するのです。これを相対的過剰人口といいます。
相対的というのは、あくまでも資本の要求に比しての労働力の供給過剰であって、生産手段に対する労働力の絶対的過剰ではないからです。
資本の蓄積過程による相対的過剰人口、つまり失業人口の発生の仕組みをこのように理解すると、現代社会において失業という存在は、けっして偶然な現象でもなく一時的なものでもないのであって、資本主義の成長とともに恒常的に存在する、いわば資本主義の必然的産物といえるでしょう。
失業人口は資本にとって必要不可欠な存在
失業人口は資本蓄積の必然的な産物であると同時に、実は資本にとって必要不可欠な存在でもあるのです。
失業人口はなにより豊富な労働力の供給源泉なのです。というのは、好景気に企業が急激に事業を拡大したい時に、いつでも必要なだけの労働力を供給できるという、いわば労働力の貯水池のような役割を果たすのです。このような意味では、現に働いている労働者を「現役軍」とすると失業人口は「産業予備軍」といえるでしょう。
失業人口はまた、現役労働者に対して低賃金を強要し、不利な労働条件を押し付けることを可能にする意味で、資本にとって好都合な存在でもあるのです。
砕いた言い方をすれば、資本主義の成長にとって失業人口は多すぎても良くないし、少なすぎても良くないといえるのです。
失業者が多すぎると、それだけ社会の購買能力が低下して需要不足に陥ってしまい、モノが売れなくなるので景気も悪くなり企業にとってはマイナスなのです。反対に失業人口がまったく無い、いわば完全雇用状態だと、先にみたように「より安い労働力」の供給源泉としての貯水池を失うことになって、これも企業にとっては不都合なことになるのです。
というわけで、失業人口は資本主義の成長とともに絶えず存在しながら、成長そのものを後ろ盾する奇妙な存在でもあるのです。
新聞報道なんかで失業率の経済指標をよく見かけるのですが、経済成長にとって失業人口の状況が大変重要だということを、こういう意味で解釈すればいいのではないでしょうか。
ちなみに、日本の場合、2021年の失業率が2.8%とされていますが、これは労働力人口に対しての数字ですが、労働力人口が2021年度平均で約6800万人なので、これの2.8%ですから約190万人の完全失業者がいるということになります。
完全に職を失っている人が190万人もいるなんて、ちょっと想像つかないことかもしれませんが、これが現実なのです。
にほんブログ村

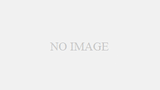

コメント