早いもので今年もあと2ヶ月ですね。
あっという間に1年が過ぎ去ろうとしていますが、生活面でみると今年は「値上げ」から始まり「値上げ」で終わりそうな一年と言っても過言ではないでしょう。
この10月の値上げだけでも、すでに6700品目の食品が値上げされました。報道されているように、年末にかけてまだまだ値上げが続きそうです。
・異常な物価の上昇
先月(9月)の消費者物価指数は前年同月比で3.0%の上昇となり、これは実に1991年8月以来31年ぶりのことです。年初来の円安がじわじわと物価に影響し、6ヶ月連続で2%を超えていたのですが、とうとう3%台にまで上昇したのです。
なかでも、家庭用耐久財は11.3%上昇し、75年以来47年ぶりの高い水準になりました。
また、生鮮食品を除く食料品は4.6%の上昇で、これも81年以来41年ぶりの上げ幅となりました。
エネルギー関連の上昇も続いており、電気代が21.5%、ガス代が25.5%も上がるなど全体では16.9%の上昇になったのです。
このように、今年の物価の上昇は異常としか言いようがないですね。
・物価上昇の主因
勿論、これは資源高もその原因ですが、なにより昨今の歴史的な円安が大きく作用しているようです。
振り返ってみると、この半年で対ドルで30円以上も値下がり(円安)しているのです。
日銀の統計によると、輸入物価の上昇に与える円安の影響度は今年の初めころは2割台だったのが、夏以降は円安が進んだことで5割超に高まっています。
米国と日本の金利差はひろがるばかりで、一向に円安に歯止めがきかない状況にあるのです。
・金融緩和と円安
にもかかわらず、日銀はかたくなに金融緩和を見直そうとはしないでいます。
景気の足を引っ張ることへの懸念からと主張していますが、何よりも金利引き上げによって一番ダメージを受けるのは、他でもなく政府と日銀なのです。
日本政府は現在、約1000兆円の債務を抱えており、金利が上がると利払いが増えるて巨額の負担増になるのです。
また、日銀は量的緩和以降策の実施以降、市場から大量の国債を買い付けており現時点で国債残高は540兆円に達しているのです。こういう状況で金利が上がると国債価格は下落して日銀も莫大な含み損を抱えることになるのです。
こういうふにみると、日銀は金利を上げないというよりも、上げれないというのが実情ではないでしょうか。
このような実情が根底に横たわっているのであって、これが昨今の円安を招いているのです。
そして、この円安によって物価が上がり消費者や企業の負担増が激化していると言えるのです。
いずれにしても、為替介入だけでは円安に歯止めをかけることは限界があり、日銀が金融緩和を見直さない限り円安トレンドは変わらないでしょう。
今後、日・米の金利差がひろがるにつれ、円安は加速度的に進むことが予測されます。
ここまで来ると年内に160円台もありえると予言しているエコノミストもいますが、国民の生活負担は増えるばかりで、国全体の景気にも影響しかねないことが懸念されますね。
にほんブログ村

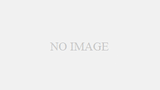

コメント