周知のように、日経平均が8月中旬以降、連日のように市場最高値を更新し、今もなお高値で推移しています。しかし、その反面、企業業績の悪化や企業倒産の増加が懸念されており、中でも中小企業の倒産増加は日本経済全体に重い足かせになり、今後の株価動向にも大きな影響を及ぼしそうです。今回は株高とは裏腹に、企業倒産が急増している実態にアプローチしてみます。
・高水準で推移する企業倒産
東京商工リサーチによると、2025年上半期(1月~6月)の全国企業倒産は4990件と4年連続で前年同期を上回っています。注目するのが負債総額1億円未満が3857件と、1996年以降で上半期では最高の77.2%を占め、小規模企業の倒産が増えていることです。
直近の7月の企業倒産状況を見ると、全国・全業種で961件と、2か月連続で前年を上回り、今年最多を更新しました。そのうち71.9%が資本金1000万円未満の中小個人企業で、5か月連続で70%台が続いています。さらに、負債1000万円未満の倒産は今年最多の57件に達し、4か月連続で前月を上回っており、57件のうち資本金1000万円は55件と96.4%を占めています。
まさに、中小企業の倒産増が顕著になっていると言えます。
また、7月の負債総額は1664憶7300万円となり、その中でも負債10億円以上の倒産は26件を超え、7月としては過去10年で最多となるなど、中堅クラスの倒産も目立っています。
コロナ禍を経て経営体力が限界に達し、資金繰りに窮した小規模事業者を中心に、物価高や人手不足、後継者難やコンプライアンス違反、税金や社会保険料の滞納などが破綻の引き金となった倒産が目立っているようです。
そんな中、人手不足の影響を受けた倒産も高水準で推移しているのが目立っており、7月だけでも49件判明し2か月連続で前年同月を上回り、昨年の3月(49件)と並んで、過去最多に並びました。
業種別でみると、「建設業」、「サービス業」が各12件で最多となり、それに「製造業」(7件)が続いています。2025年1月~7月の累計は251件で、過去最多となった前年同期(213件)を上回るペースで推移しています。
・倒産リスクの高い企業も急増
倒産までには至らないが、倒産リスクが高いとみなされる企業も増えています。
帝国データバンクは、企業が1年以内に倒産する確率を10段階グレードで示す指標「倒産予測値」のデータを基に、今後のリスク動向を調査したのですが、倒産予測値が高い企業(グレード8~10)は、今年の6月時点で全体の8.7%にあたる12万8552社となり、2024年12月と比べ1592社増加したと分析しています。これは、厳しい経営環境に対応できない企業でリスク顕在化が進んでいることを表してします。
業種別でみると、「製造業」が3万3465社で最多、昨年12月と比べ4894社増加しており、次に「建設業」が3万20社(同1203社増)となっています。
また、業種内の全企業に占める高リスク企業の割合では「出版・印刷・同関連産業」が41.0%で最多となっており、「飲食店」が38.3%、「皮革・同製品・毛皮製造業」が37.6%と続き、全体平均(8.7%)の4倍以上となってます。
ちなみに、2025年上半期に倒産した企業のうち、2024年12月時点で高リスクに分類さていた企業の割合は全体で41.0%で、これに対し「運輸業」は73.3%、「飲食料品小売業」は76.6%、「飲食店」は69.2%と、高水準で市場淘汰が進んでいることが示された。
倒産リスクの高い企業を売上高別でみると、「1億円未満」が8万2491社で全体の64.2%を占めて最も多く、「10億円未満」の企業でみると、全体の96.6%で大半を占めています。
また、従業員別では「5人未満」が8万1352社で最も多く(63.3%)、「5人~10人未満」が2万1035社(16.4%)と続き、10人未満の小規模企業(79.7%)に集中していることが明らかになっています。
帝国データバンクは、米国との相互関税15%の影響、コロナ借り換え保証の返済本格化、物価高、人手不足などから、当面は経営環境の好転は乏しいと指摘しており、さらにリスクが複合的に作用し、中小企業の倒産リスクは一段と高まる可能性があると警鐘を鳴らしています。
・大企業の景況感もマイナス
そんな中、中小・零細企業だけでなく、大企業の景況感もマイナス傾向に陥っています。
財務省と内閣府が発表(8月12日)した4~6月期の法人企業景気予測調査によると、大企業全産業の景況判断指数はマイナス1.9となりました。マイナスは5四半期ぶりで、米国高関税政策への影響懸念などから、製造業が2期連続マイナスとなったほか、仕入れ価格の上昇などを受け、非製造業も11期ぶりにマイナスに落ち込んだようです。
大企業製造業は全体でマイナス4.8で、なかでも高関税措置の影響などにより鉄鋼業はマイナス29.1、自動車・同付属品製造業はマイナス16.1と、いずれも大幅に減少しています。
非製造業はマイナス0.5で、仕入れ価の上昇や建材需要の減少で卸売業がマイナス0.8となっています。
また、中堅企業全産業はマイナス0.9、中小企業全産業はマイナス12.3に減少しました。
このように、景況感がマイナスに陥る中で、上場企業の2026年3月期の純損益も前期比で約8%の減益を見込まれており自動車など製造業を中心とした不振が目立っているようです。
以上のように、最高値を更新している株式市場での活況の裏腹で、企業倒産が急増し、大企業を含め景況感は減少しつつあり、株価と実体経済との乖離が浮き彫りになっているようです。
とりわけ、注目すべきは中堅企業を含め中小規模企業の倒産増の影響は、規模としては日本経済への影響は小さくても、今後、全国に波及すれば地方経済の疲弊に繋がり、経済全体へ重い足かせになるのは間違いないでしょう。
国内企業全体の約99%を占める中小企業は、個人消費を左右し、日本経済を支える基盤であることは言うまでもありません。その多くの中小・零細企業が倒産に追い込まれており、倒産リスクが高まっている現実は、今後の株式相場を見据えるうえでも決して見逃せないでしょう。
にほんブログ村
にほんブログ村
ブログランキングに参加しております。上のバナーをクリックして応援お願いします。
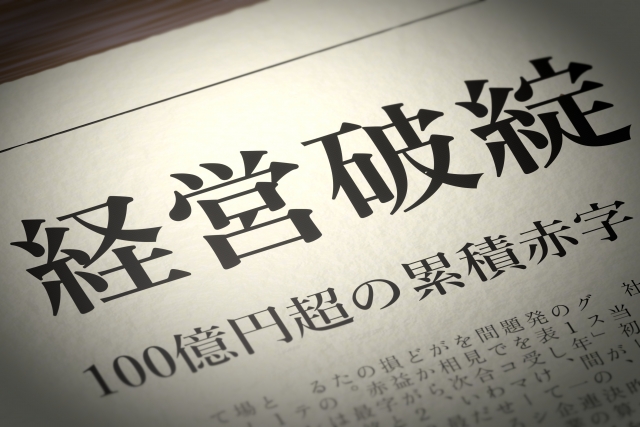


コメント