周知のように、参議院選挙の最大の争点とされている物価高対策として、給付か消費税減税なのか、各党の選挙公約に対して注目が集まっています。はたして、有権者の判断がどうでるのか選挙結果を待ちたいところですが、意外に消費税がどのように導入され、利用されているのか知られていないようです。それを踏まえて、消費税減税による財源確保や経済効果についてまとめてみましょう。
・消費税導入とその背景
日本で導入されて以来約30年が経つ消費税、平成の歴史とともに歩み続けた消費税は、今や10代や20代の若い世代にとって物心がついた頃から存在していた税金であり、私たちの生活においてもっとも身近なものとなっている税金の一つではないでしょうか。
消費税とは、文字通り消費者が商品などを買う際に負担する税金のことですが、消費者が直接税を払っているのではなく、消費税を受け取ったお店などの事業者が消費者の代わりに納めるのです。
つまり、消費税は税を納める人と税を負担する人が異なる間接税と呼ばれる税です。
ちなみに、所得税や法人税のように税を納める人と税を負担する人が同じである税金は「直接税」といい、税を納める人と税を負担する人が異なる税金を「間接税」というのですが、酒税のように消費税も間接税に属します。
消費税導入前の間接税は、特定の物品やサービスに課税する個別間接税制度が中心で、物品税という贅沢品に対して税金をかける税制がありました。これは、物品ごとに必需品か贅沢品かを特定し、贅沢品にだけ課税する税金です。例えば、毛皮製品やゴルフ用具、コーヒーなどがそうでした。
ところが、所得水準の上昇や国民の価値観の多様化が進むにつれ、贅沢品として課税すべき物品やサービスを客観的基準で判断することが事実上困難となり、また、お金を使う対象が物品からサービスへと比重が変化する中で、物品とサービスの間の負担の不均衡という問題があらわれるようになり、税制全体としての負担の公平性を高めることや、個別間接税制度が直面している問題を根本的に解決することを目的として、消費全体に広く薄く負担を求める消費税の創設が必要と考えられたのです。
消費税の創設が導入されたもうひとつの大きな理由として、高齢化社会の対応という問題がありました。日本は、世界の主要国においても例をみない速さで人口の高齢化が進んでおり、年金、医療、福祉のための財源確保が喫緊の課題となっていたのですが、従来のような現役世代に頼った税制では、今後、働き手の税負担も限界に達するほか、納税者の重税感や不公平感が高まり、事業意欲や勤労意欲も阻害することになりかねないことが懸念されました。
こうした社会問題に対する懸念も追い風となり、1998年12月30日に消費税法が施行され、1989年4月1日から適用されることになったのです。
・消費税引き上げと税収の使途
このように、消費税は1989年(平成1年)に導入され、当初は3%からスタートしたのですが、これまで3度にかけて引き上げられました。
1回目は、8年後の1997年4月1日に5%に引き上げられ、2回目は、その7年後の2014年4月1日に8%に引き上げられました。そして、その5年後の2019年10月1日に10%へと3回目の引き上げが行われたのです。
そして、3回目の引き上げの時に、10%の標準税率とともに軽減税率を制定したのです。
軽減税率とは原則として10%である消費税の税率を、定められた一部の品目だけ8%とする制度です。
これは、消費税率が8%から10%に引き上げられる際に、消費者の負担を緩和する目的に設けられたのですが、その対象には酒類や外食を除く飲食料品と定期購読契約が締結された週2回以上の新聞とされています。こうして、現在の消費税の税率は10%の標準税率と8%の軽減税率で構成されています。
また、消費税は国が徴収する国税としての消費税と地方自治体の税収としての地方消費税に構成されています。例えば、1997年の1回目の5%へ引き上げの際に、国の消費税収は4%と地方消費税は1%で、2回目の2014年の8%への引き上げの際には、国が6.3%で地方消費税が1.7%となっています。そして、3回目の2019年、標準税率10%の内で、国の税収は7.8%、地方消費税は2.2%となっています。
これが現在の国税と地方消費税の税収の内訳となっているのです。
これを令和7年度の消費税収の予算でみると、消費税全体で31兆4307億円が設けられており、その内、国の消費税は24兆9080億円、地方消費税は6兆5227億円となっています。
さて、このように徴収されている消費税収は、財務省「消費税の使途に関する資料」によると、年金、医療、介護、子ども・子育て支援対策の4つの社会保障の経費に充てられています。
例えば、令和7年度の予算によると、①年金;14兆3000億円、②医療;12兆3000億円、③介護;3兆7000億円、④子ども・子育て支援;3兆6000億円となっています。
また、地方消費税の一部は自治体などが行う社会保障施策に使用されるケースもあり、生活保護や児童福祉などの社会福祉関連や感染症予防や健康増進対策などの保険衛生などに活用されています。
・問われる消費税減税の財源問題と経済効果
このように、消費税は国民の生活のなかで重要な役割を果たしているのは疑いの余地はなく、税金の使い道を理解すると普段支払っている消費税の重要度もより強く感じられるのも確かではないでしょうか。
さて、7月20日の投票日に向けて行われている今回の参議院選挙では、先述したように物価高対策として各党が「給付か消費税減税」を選挙公約として打ち出し熾烈な選挙戦を繰り広げているのですが、物価高対策としてどちらが有効なのか、国民は何を望んでいるのかは選挙結果によって判断されると思われます。いずれにせよ、消費税のあり方が大きな焦点になるのは間違いないでしょう。
今回の参院選では、おおむね与党が「現金給付」、野党が「消費減税」と対立している構図で争われているのですが、野党の中でも消費税を一律に関税するという案と、食料品に限定して減税すべきとする案があり、また、消費税の廃止や期限付きの5%や0%への減税など、党によって様々な政策を公約として打ち出しています。
問題は選挙ということもあり、公約として大袋を広げて票を勝ち取ろうとする向きも全くないわけではないと疑念するところもあるのですが、大きく分けて懸念される点は物価高対策としての減税効果がどうかという問題と、もう一つは減税分の財源をどう確保するかという点に帰着するでしょう。
まず第一に、物価高対策としての減税効果がどうかということです。
多くの党が政策公約として打ち出している消費税5%への減税を取ってみると、年間約15兆円もの減収が見込まれるようですが、それに見合った物価高対策としてしての減税効果が得られるのかという点では懐疑的な見方が少なくないようです。
事実、経済学者達を対象にした調査によると、消費税減税について実に85%が否定的で、その理由として一度引き下げを行なうと元にもどすことが困難だという点と、物価高対策としての減税効果は限定的で、税収の損失に見合わないとしていることです。減税効果が限定的であることは、ヨーロッパでの複数の先行事例に対する分析に基づいているようです。
二点目は、減税の財源をどう確保するかということです。
先述したように、例えば消費税を5%に引き下げることによって、年間約15兆円の減収が見込まれるとすると、消費税収入によって賄われている社会保障制度へのしわよせが当然考えられますが、その穴埋めをどのように確保するのかが問われます。
この問題に対して、税収の上振れや国の基金の余剰資金の捻出、法人税率の引き上げや防衛費の引き下げなど税制の見直しと予算の見直し、成長戦略による税収増で賄うなど、各党は様々な形で財源確保を主張していますが、一時的ではなく持続的に、そして確実に確保していくという点では、どの問題をとりあげてみても容易ではないように思えてなりません。
いずれにせよ、物価高は収まっても社会保障費の削減など別の形で影響が出てしまっては本末転倒で、国民の暮らしを支えている予算を削らず実現することができるのか、注目せざるを得ません。
依然と値上げの波が押し寄せ、家計の負担が増すばかりの今日ですが、消費税減税が本当に国民の負担軽減になるのか問われているのではないでしょうか。
にほんブログ村
にほんブログ村
ブログランキングに参加しております。上のバナーをクリックして応援お願いします。

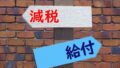

コメント