20日の投票日を迎えて終盤の追い込みに入っている参議院選挙ですが、その背後では日本の財政赤字に対する不安が高まり、債券市場では記録的な利回りの上昇が起きています。そのきっかけになっているのが、いわゆる「5・20ショック」です。今回は今、日本の債券市場で何が起こっているのか迫ってみたいと思います。
・「5・20ショック」とは
去る5月20日、財務省が新規発行20年国債が記録的な不調、つまり売れ行きが悪く、十分な買い手がつかなかったのです。要するに、国債が思うように売れない状況に陥り、これを受けて市場では30年国債の利回りが一時3.1%台と過去最高水準になったのです。
金利上昇は国債の価格低下、つまり価値の下落を意味します。償還期間が10年を超える国債は超長期国債と呼ばれるのですが、今回の30年債をはじめとする超長期国債の金利上昇は、発行する日本政府の将来の財政状況の悪化に対する市場の警戒感が表面化したとみられます。この事態を財務省関係筋では「5・20ショック」と表現しているのです。
そもそも、日本の将来に対する不安の最大の原因は、世界最悪とも言われている財政赤字にあるのですが、その深刻な状況に解消のメドが立たないでいます。
国の借金の総額は今年度末には過去最大の1129兆円に達する見通しですが、さらに厳しいのは金利が上昇すると国の借金返済、とくに国債の利払い費がもっと膨らむことになることです。国の毎年の借金返済である国債費は現在、元本の償還費が61%、利払い費が37%を占めているようですが、金利が1%上昇すると、2034年の国債利払い費が8兆7000億円増えると試算されています。
日本国債の格付けを見ると、韓国や台湾より下(A1/A+~A2/A)で、G7でイタリアの次に低いとされているのですが、この格付けが引き下げられてしまうと金利が一段と上乗せされるます。信用が下がった分、金利を上乗せしないといけなくなるからです。こうなると民間企業に対する格付けも連動して下がってしまい、政府だけでなく企業の資金調達まで苦しめることになるのです。
日銀は2013年の異次元緩和措置以降に国債を大量に買い続け、昨年末で国際残高の約半分を保有する異常事態に至ったのですが、昨年、金融政策の正常化をめざしてから国債の買い入れを段階的に減らす方針を示し、3%(年率換算)の緩やかなペースで減らしてきました。そこに、今回の「5・20ショック」に代表される国債をめぐる不安定な状況が生じたのです。
そこで、財務省は6月20日、国債入札に参加する主な金融機関を対象とした会議で、今年度の国債発行計画の修正案を示す異例の事態に至ったのです。要するに、超長期国債を高い金利で売る事態を避けるために発行額を減らす一方で、逆に買い手にとって相対的にリスクが少ない短期債や個人向け国債を増やして帳尻を合わせる措置を取ったということです。
しかし、短期の国債が増えると金融政策の影響をまともに受けることになり、市場金利がハイペースで上昇した場合は利払い費が膨らみ、財政をさらに圧迫する恐れがあるのですが、それが分かっていても発行計画の修正をせざるを得ない事態に追い込まれているのです。
・日本の国債残高の推移
政府債務の残高は1000兆円を超えており、「破綻寸前」といった表現をよく見かけますが、現在どのような状態にあるのか簡単に確認しておきましょう。
日本では戦後の復興期に「復興国債」が発行され、昭和40年代以降は高度経済成長の後押しとして財政投融資を含む形での国債発行が活発になりました。そして、バブル崩壊後、1990年代の長期不況期には「景気対策」としての国債発行が加速していきます。
2008年のリーマンショック以降、一層の増加を見せ、新型コロナウイルス感染対策による大規模な補正予算の影響で、2020年以降も急激に積み上げられ過去最高を更新し続けており、毎年の税収ではまかないきれない予算を補うために、赤字国債が常態化している状況です。
このような過程を経て、日本の国債発行額は膨大な額に至っているのですが、財務省の発表(2025年2月)によると、2024年12月末の国債発行残高は約1173,5兆円で、これは日本の名目GDP(約560兆円)の約2倍近い水準になります。債務比率でみると、実に216,2%に至っており、これは先進国の中でも際立って高い数字と言えます。
・危機的な日本の財政事情
こうした状況の渦中、4月から5月にかけての超長期金利の急騰に引き続き、直近の7月に入っても債券市場では長期金利が急上昇しているのが目に付きます。
長期金利の代表的な指標である10年物国債の流通利回りが、東京債券市場で一時1.595%に上昇しました。これは、2008年10月のリーマンショック直後以来、約17年ぶりの高水準なのです。
また、新発20年国債の利回りが(7月14日現在)2.625%まで上昇し、2000年以来の高水準を更新したのです。国債は売られて価格が下がると利回りが上昇する仕組みで、参議院選挙の結果次第では拡張的な財政政策が行われる可能性があることから、財政状況の悪化を懸念して国債を売る動きが強まっていると見られています。
金利の上昇が常態化しつつあり、今後さらなる金利上昇が続いた場合、財政運営に大きな影響をあたえるのは避けられないでしょう。
借金をしながら業務や事業を続けている経済主体にとっては、予定通りに返済を進めえていけるかが、先行きも存続できるか否かの決定的な鍵を握るのです。これは民間企業だけでなく、国も同様です。
日本は、これまで国債残高を右肩上がりで積み増し続けてきた結果、その規模はGDP比で世界最悪水準にあることは先述した通りですが、それにもかかわらず、財政運営を大した困難も経験せずに続けてこられた要因は、ひとえに利払い費が抑制されてきたことによると言えます。
国債残高が雪だるま式に増えてきたのとは裏腹に、利払い費は1980年代後半から90年代末までは、ほぼ10兆円前後の横ばいで推移し、その後の2000年代前半は増えるどころか逆に減少しているのです。
これには、日銀が異例の「ゼロ金利政策」や多額の国債を買い入れる「量的緩和政策」を実施したことが大きく影響しています。多額の国債買い入れによって長期金利までもが一時は1%以下の低水準になった結果、国の財政運営は極めて大きな「恩恵」を受けることになったのです。
2013年に、日銀は2000年代前半の「量的緩和政策」時代と比べものにならない巨額の規模で国債等を買い入れる「量的・質的金融緩和」を開始したのですが、それ以降、このいわゆる「異次元緩和」は実に11年間にわたって続けられ、日銀のこうした金融政策の恩恵を受けながら、日本の利払い費は2010年代後半にはさらに減少しました。
ところが、コロナ危機を脱却するころから、欧米主要国の経済が相次いで高インフレ局面に急転換し、その影響が日本にも及ぶことになり、日銀も遅まきながら昨年3月に「異次元緩和」に終止符を打ち、マイナス金利政策から脱却して、2度にわたり追加利上げを行うほか、国債の買い入れの減額にも着手したのです。
このような金融情勢の下、財務省の試算によると、2025年度当初予算政府案では10.5兆円が計上されている利払い費は、9年後の2034年度には実に25.8兆円に達することが見込まれています。
一般会計の税収が78.4兆円しかないにもかかわらず、115兆円あまりの歳出・歳入予算を組んでいる日本にとって、この先25兆円を上回る利払い費を果たして負担できるのかが危ぶまれているのですが、今後、金利の動向如何によっては一層厳しい状況に追い込まれるのは言うまでもありません。
日本の財政運営の先行きには、まさに赤信号が点滅していると言えるでしょう。
それに加えて、当面として懸念される点は、「5・20ショック」に顕在化したように超長期を中心に日本国債の買い手不在が深刻化していることです。生命保険会社に限らず、安定消化の主役であるはずの銀行も、金利上昇による「コア預金モデル」(金利上昇局面を考慮に入れ、金利リスクを管理するために、流動性預金のうち長期間滞留する部分のコア預金の実質的な満期を計測するモデル)の見直しなどを背景に、長期国債を買えない状況に直面しています。
先述したように、日銀の国債保有残高は現時点で約560兆円で、「量的・質的金融緩和」政策を開始した2013年以前までは100兆円にも満たなかったのです。金融政策正常化に伴い、仮に当時の水準まで残高を減らすとすれば、500兆円弱の国債を民間部門に移る計算になります。新たな保有主体を見つけなければ、超長期国債にとどまらず、国債市場全体の需給が緩む懸念が強まり、金利を一層押し上げかねないのです。このように、日本財政の基盤そのものである国債の安定消化が揺るぎ始め、財政危機と言っても過言ではない事態に直面しつつあると言えます。
いずれにせよ、このような財政状況の中、大詰めを迎えている参議院選挙の結果次第では、金融情勢が大きく揺れ動くことも考えられ、選挙の行方が大変気になるところではないでしょうか。
にほんブログ村
にほんブログ村
ブログランキングに参加しております。上のバナーをクリックして応援お願いします。


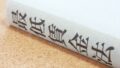
コメント