自・公与党の大敗で幕がおりた参議院選挙から早いもので、すでに1か月が過ぎました。選挙の最大の争点とされた物価高対策として、与党の「給付案」と、違いはありますが総じて野党の「消費税減税案」が公約として国民に訴えた選挙戦だったのですが、選挙が終わるとなんのおそさたもなく、あれは一体何だったのかと疑念を抱かざるを得ません。そこで、今回は選挙公約として唱えられた「給付と消費税減税」の行方についてまとめてみます。
・選挙公約だった「給付と減税」
酷暑の中、立候補者の方々が一応に物価高対策を熱弁していた参議院選挙でしたが、一番の争点として取り上げられたのが、給付案と消費税減税案だったのは記憶に新しいですね。
自民・公明の与党が公約として打ち出した給付案は、周知のように一律1人2万円を給付し、低所得者と子供に対しては4万円の給付をすることを熱弁しました。減税措置には時間がかかるとして、物価高に苦悩する国民への早急な対策は給付が適しているとの判断によるものでした。スピード感ある対策としての給付を強調したのです。
それに対して、結果的に過半数を獲得した野党は、消費税減税を柱にして公約を示し、食料品をゼロにすることや、一律5%の消費税減税、または全ての商品に対してゼロにするといった減税案を打ち出しました。
しかし、いざ選挙が終わってみると、すでに1か月が過ぎようとしている今日も、これらの物価対策は国民の生活を守るための喫緊の課題であるにもかかわらす、なんのおとさたもありません。
値上げラッシュは留まる気配はなく、物価高は続く中で一刻も早い対策がのぞまれているのですが、与党の給付案も野党が熱弁していた消費税減税案に対する実効手続きは全く見えないままです。
・見通しが立たない「給付と減税」
そうこうしている間にも、コメ価格をはじめ物価高はやむ気配が見えません。
値上げラッシュは留まるところを知らず、参議院選挙直後の8月の場合、主要な食品メーカー195社における家庭用中心の飲食料品の値上げは1000品目を超え、値上げ1回あたりの値上げ率は平均で11%になりました。単月の値上げ品目数としては3か月連続で1000品目以上の値上げとなり、また、1月以降8か月連続で前年同月を上回りました。
そんな中、総務省の発表によると、7月の全国消費者物価指数は(生鮮食品を除くコアCPI)、8か月連続で3%台となりました。
このような物価高の中、早く対策を講じてほしいというのが国民の一番の願いなのです。
勿論、給付案や消費税減税案に対してそれぞれ意見の違いはあるのですが、いずれにせよ、何らかの対策が喫緊の要望であるのは間違いないはずです。
ところが、選挙後の動きを見ると、給付も減税も見通しが立たないまま、自民党総裁選挙実施などの理由で政治的空白が生じるリスクが高まっており、何ら物価高対策が進まない現状に批判の声が高まっています。
政府・自民党内では、公約として打ち出した給付案に対して、「少数与党化」で野党から賛成を得るメドは立たず、世論の理解も得られてないことから、全国民を対象にした給付の見直し論まで出ている状態で、迅速な給付を訴えていましたが、制度設計は進んでいないのが現状のようです。
また、消費税減税案も野党同士でまとまる気配が見えず、結局は選挙で最大の争点であった物価高対策が選挙後に飛んでしまいかねない状況にあるのです。
・どうなる物価高対策
自民・公明の与党はもともと、給付の裏付けとなる2025年度補正予算案を秋の臨時国会で成立させ、年内の給付開始を目指していたのですが、参議院選挙での大敗を受け、政府・党内からも給付対象などの再考を求める声が出ており、実現に不可欠となる野党との調整も進んでいないようです。
臨時国会に補正予算案を提出するには、制度設計を急ぐ必要があるのですが、自民党内では臨時総裁選の実施の是非を問う作業が進められており、物価高対策としての公約は後回しになっているのも否めないようです。
そればかりではなく、そもそも選挙前から給付に反対の野党も複数で、選挙後における世論調査にも給付に対する反対世論が少なくないのも現実で、給付の実現にはハードルが高いと言えるでしょう。
他方、消費税減税の実現は制度的変革を伴い、時間的に物価高対策としての即効性には欠けるところもあり、直近の物価高を軽減させる対策としては実感の乏しい側面があるのも事実でしょう。
とは言え、物価高対策が選挙戦で票を得るための「道具と化」させることは絶体許されることではないはずです。今、日本の政治には、一刻も早く与・野連携の下、物価高対策の実現に向けて対処してもらいたいということが国民の願いであることを、今一度肝に銘じてもらいたいですね。
にほんブログ村
にほんブログ村
ブログランキングに参加しております。上のバナーをクリックして応援お願いします。

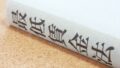

コメント