先日、2025年度の最低賃金が1118円を目安とすることが決まりました。メディアでも大きく取り上げられ注目を集めていますが、実質賃金が上がらない状況だけに今後の行方が気になるところです。今回は最低賃金とは何か、その目的と決め方、最低賃金が与える影響などについてまとめてみます。
・最低賃金制度
最低賃金制度とは、国が賃金の最低限度を定め、雇用者がその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払うことを義務付ける制度です。この制度は、労働者の生活の安定、労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保、しいては国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、日本では1959年に最低賃金法が制定されたことにより導入されました。
最低賃金は、正社員、契約社員、派遣、アルバイト、パートなど、雇用形態にかかわらずすべての労働者が対象です。ただ、最低賃金の計算対象となるのは基本給のみで、時間外割増賃金やボーナス、通勤手当や皆勤手当、休日割増賃金や深夜割増賃金などは除外されます。
最低賃金の地域格差について、マスコミなどでよく目にすることがありますが、最低賃金は各都道府県ごとに定められる最低賃金である「地域別最低賃金」と、地域別最低賃金より高い水準で定められる「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
最低賃金法により、仮に最低賃金額より低い賃金が労働者と雇用者双方の合意によって定められたとしても、その部分は法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。最低賃金を下回る賃金を支払った場合、罰則が科せられることがあり、地域別最低賃金の場合は50万円以下の罰金、産業別最低賃金の場合は30万円以下の罰金が科せられます。
最低賃金は、厚生労働省の最低賃金審議会で審議され、各都道府県の労働局長によって決定されます。最低賃金の決定にあたっては、労働者の生計費や類似の労働者の賃金、企業側における通常の事業の賃金支払い能力などが考慮されます。
新たな最低賃金の改定は、通常は毎年の7月に審議され、決定された新しい最低賃金は10月1日からの適用となります。
・2025年度の最低賃金の改定
すでにマスコミが取り上げているように、2025年度の最低賃金(時給)が1118円を目安とすることが中央最低賃金審議会の小委員会で決まりました。
現在の最低賃金の全国平均1055円から6.0%(63円)の過去最大の大幅な上昇で、初めて1100円台に突入する見通しとなりました。長引く食料品の物価高への対応を重視した形になったようです。また、これによりすべての都道府県で時給1000円を超える水準が実現する見込みとなりました。
ちなみに、経済協力開発機構(OECD)のデータ(2024年)によると、日本の最低賃金は、フルタイムで働く正社員らの賃金中央値の46.8%にとどまり、フランスの62.5%やイギリスの61.1%などに比べてかなり低く、先進国の中で見劣りする日本の最低賃金水準も検討された結果のようです。
最低賃金と正社員の賃金の差は、非正規労働者と正規労働者の格差を招くため、大幅な引き上げは格差解消にもつながると期待されているようです。
しかし、今回示された6.0%の水準は今年の春闘の中小企業の平均賃上げ率(4%台)を大きく上回り、地方や小規模事業者を含む企業の支払い能力を踏まえれば極めて厳しい結果で、とりわけ賃上げの余力に乏しい中小企業にとって深刻な経営課題になるでしょう。
・最低賃金大幅改定の副作用
物価高が収まる気配が見えない中、実質賃金が下がり続けている状況で労働者にとっては最低賃金の引き上げは生活の支えとして一定の意義はあり、消費を下支えする効果は一定程度否めないのですが、経済成長をけん引する決定打にはなり得ないと見るのが大勢のようです。
その反面、副作用も懸念されるところであって、企業にとっては人件費コストが重くのしかかり、先述したように、とりわけ中小企業は価格転嫁力が乏しく、結果的に投資や雇用に抑制的な影響を及ぼす可能性があると言えるでしょう。
すでに、過去最大の5年連続の引き上げが中小・零細企業の負担は増しており、中小企業庁の調査では、労務費の増加を転嫁できている中小企業は、今年3月の時点で48.6%しかなく、さらなる賃金の引き上げは経営の悪化を引き起こす恐れもあるのです。
また、これにより人手不足に拍車がかかることも懸念されます。時給が上がればその分、所得税が課され始める「年収の壁」に短時間で達するため、パート従業員らの「働き控え」が今より広がる可能性があるからです。
とりわけ、懸念されるのは物価上昇に追い打ちをかけ、さらなる物価上昇を招く恐れも否めないのです。すでに昨今の物価上昇の要因として賃金アップを価格転嫁で対応する企業の姿勢が指摘されており、さらなる賃金上昇が一層の物価の上昇を招く、いわば「物価と賃金の悪循環」を加速させる可能性があるのです。
このように、雇用への影響や人手不足を加速させ、物価の上昇に追い打ちをかけることへの副作用は決して少なくないでしょう。
最低賃金の大幅な引き上げは、賃上げによる消費の底上げを期待する政府の戦略の一環と思えるのですが、しかし、中小企業の経営環境や労働供給の制約、また地域間の格差といった多層的な課題を解決するには不十分で、制度的な支えや構造的な改革を推進することが問われており、それを伴わない最低賃金の引き上げは、副作用の方が大きくなる可能性も否めないのではないでしょうか。
にほんブログ村
にほんブログ村
ブログランキングに参加しております。上のバナーをクリックして応援お願いします。
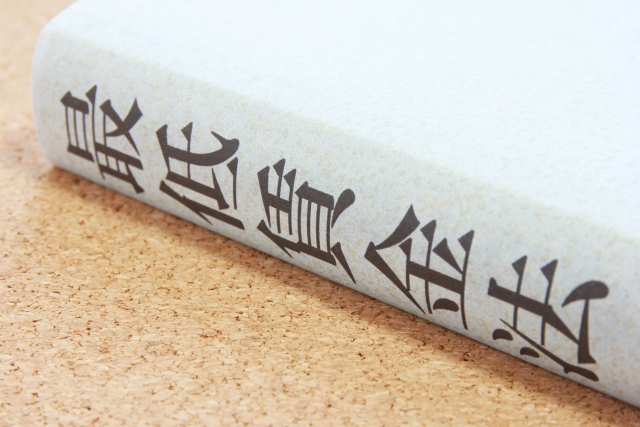


コメント